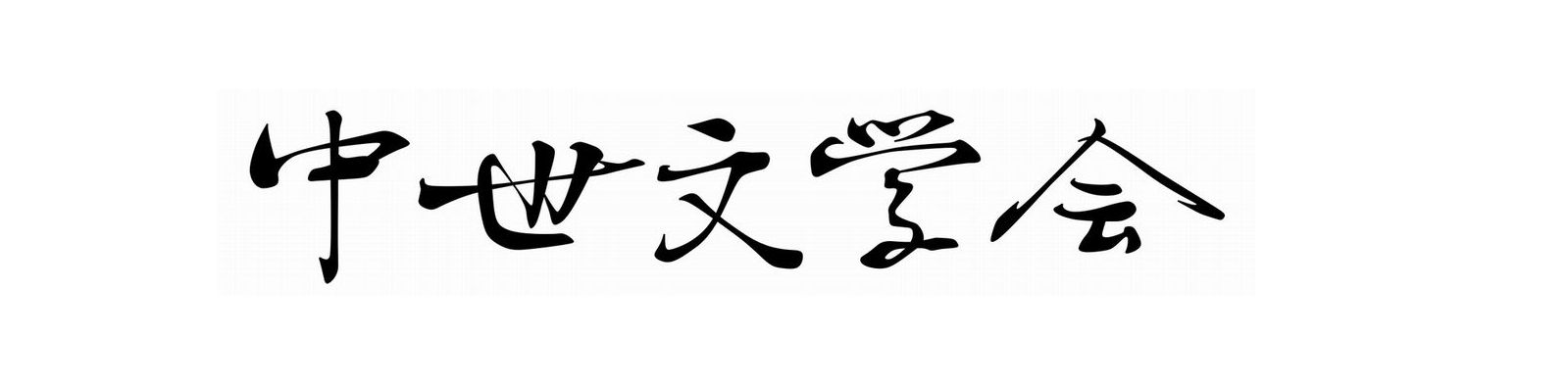ハイブリッド開催
会場校 大谷大学 京都/本部キャンパス 〒603-8143 京都府京都市北区小山上総町
第1日 10月25日(土) 受付開始 13:00 会場 慶聞館1階K101教室
開会の挨拶(14:00~14:10) 大谷大学文学部長 藤元 雅文氏
公開講演会(14:15~17:00)
『平家物語』と「英雄」 青山学院大学名誉教授 佐伯 真一氏
酒呑童子絵巻研究の諸問題 国文学研究資料館名誉教授 小林 健二氏
第8回 中世文学会賞授与式(17:05~17:20)
懇親会 (18:00~20:00)
第2日 10月26日(日) 受付開始 9:30 会場 慶聞館1階K101教室
研究発表会〈午前の部〉(10:00~12:30)
武具表現から読む『平家物語』 大谷大学(院) 古賀 春菜氏
世阿弥作「檜垣」について―老女の舞が意味するもの―
京都大学文学研究科(非) 奥田茉莉子氏
狩野山雪筆「長恨歌図巻」の表象行為に関する一考察
福山大学大学教育センター 井上 泰 氏
昼食・休憩(12:30~13:30)
大谷大学博物館特別展 ワークショップ(13:30~15:00)
「物語をつたえる絵とことば」 司会:佐藤愛弓氏
担当:江口啓子氏・末松美咲氏・本井牧子氏・佐藤愛弓氏
研究発表会〈午後の部〉(15:15~16:40)
宗祇画像の一伝本―立命館大学蔵本の意義― 立命館大学 川崎佐知子氏
猪熊方「禅仙」を介した『天狗絵詞』などの背景―中世文学史の背景の一端―
実践女子大学 牧野 和夫氏
閉会の挨拶 明治大学 牧野 淳司氏
※発表要旨はこちら
※2日目ワークショップの案内はこちら
※大谷大学へのアクセスはこちら
※大谷大学博物館では特別展「物語をつたえる絵とことば」が開催されています。詳細は大谷大学博物館のHPをご覧ください。大谷大学博物館HP特別展はこちら
※2日目大谷大学博物館特別展ワークショップについては、オンライン配信を行いません。
※参加申し込みについて。10月15日(水)締め切り→19日(日)まで延長します。なお、懇親会の申し込みは15日で締め切りました。→参加申し込みは締め切りました。
(10月20日更新)21日までに、参加を申し込まれた方の登録アドレスに、大会の参加方法を送信します。
(10月21日更新)参加を申し込まれた方の登録アドレスに、大会の参加方法を送信しました。
メールが届いていない場合、ご登録のアドレスに記載ミスがあった可能性があります。事務局までお問い合わせください。なお、URLを含むメールは、自動で迷惑メールフォルダに振り分けられる可能性があります。お使いのメールソフトの迷惑メールフォルダのご確認もお願いします。